 安齋
安齋警察官採用試験の合格に特化したオンラインスクール「警志塾」を運営している安齋です!
「警視庁」と「警察庁」と「公安」。
ニュースやドラマなどで耳にすることの多いワードですが、それぞれ一体何が違うのかと思う人も多いでしょう。
そこで今回の記事では、警視庁・警察庁・公安の仕事内容やなり方、立場など、各機関の違いについて解説していきます。
将来警察になりたいと思っている人は、この記事を読んで正しい知識を身につけ、モチベーションアップにつなげましょう。
\警視庁採用試験の情報を発信/
警視庁・警察庁・検察庁・公安の違いとは?


警視庁や警察庁、検察庁、公安はいずれも、治安や法律に関わる組織のため混同されがちですが、それぞれの役割や立場は大きく異なります。
警察官を目指す方なら、自分が希望する都道府県警察に関することだけでなく、警察に関わる組織の概要について把握しておくことも大切です。
具体的な役割や立場の違いは、以下の表を参考にしてください。
| 名称 | 主な役割 | 所属・組織 |
|---|---|---|
| 警視庁 | 東京都の警察行政機関 | 地方自治体 |
| 警察庁 | 全国の警察を統括・管理 | 国 |
| 検察庁 | 犯罪捜査・起訴不起訴の決定・公判の担当 | 法務省管轄 |
| 公安 | スパイ・テロ対策など国家安全に関する調査・警備 | 内閣府や法務省など各所 |
それぞれの組織が担う領域は一部重なりながらも、本質的な役割と立場は明確に分かれています。続いては、それぞれの組織についての仕事内容やなり方などを紹介します。



各組織がどんな仕事をしているのかもっと細かく理解しておきましょう!
警視庁とは


警視庁は、東京都を管轄している「都」の警察行政機関です。
各都道府県には、北海道警察(北海道警)や大阪府警察(大阪府警)など、それぞれの都道府県を統括する警察機関があります。警視庁はそれらと同等の機関なのですが、東京都警察とは呼ばずに、警視庁と呼んでいます。
「庁」と名がついていますが、職員は地方公務員で、省庁とは異なる機関です。
ちなみに、2024年で警視庁は創立150周年を迎えました。
警視庁の仕事内容
警視庁の主な仕事内容は、東京都内の治安維持を中心とした多岐にわたる警察業務を遂行することです。
首都の安全を守る警視庁だからこそできる仕事も多く存在します。
- 天皇陛下や皇族、国内外の要人警護
- 国際テロやサイバー攻撃への対応
- 主要国首脳会議(サミット)等の大規模警備が必要な際の警備(派遣)
もちろん犯罪捜査や交通整備、地域パトロール、災害・事故発生時の救助活動など、基本的な業務も行います。
東京都民の暮らしを支える以外に、前述の要人警護やテロ対応なども行うため、東京を守るだけでなく、国を守る一端を担っていると言ってもよいでしょう。
警視庁で働くためには
警視庁の職員として働くためには、警視庁が行う採用試験に合格しなければなりません。
職員募集には、犯罪を直接取り締まる「警察官」と、警察官の業務をバックアップや事務を行う「警察行政職員」の2種類が存在します。
試験の種類を以下にまとめました。
| 警察官採用試験の試験分類 | 警察行政職員採用試験の試験分類 |
|---|---|
| Ⅰ類 (大学卒業程度) | 【警察行政職員Ⅰ類】 事務、土木、建築、機械、電気、心理 |
| 【専門職種Ⅰ類】 通訳(タイ語・スペイン語・タガログ語・ネパール語)、 交通技術、鑑識技術(物理・文書鑑定)、 自動車運転免許試験官 | |
| 【専門職種Ⅲ類】 航空機械技術 | |
| Ⅲ類 (高校卒業程度) | 【警察行政職員Ⅲ類】 事務、電気 |
| 【警察行政職員Ⅱ類】 保健師 | |
| 【技能系】 自動車整備、海技、電話交換、印刷製本、一般用務 | |
| 【障害者を対象とする警察行政職員Ⅲ類】 事務 |
上記の試験分類に加え、採用試験ごとの試験内容も以下にまとめました。
| 警察官採用試験の内容(Ⅰ類・Ⅲ類共通) | |
|---|---|
| 第1次試験 | 教養試験、論(作)文試験、国語試験、適性検査 |
| 第2次試験 | 面接試験、身体検査、体力検査、別の適性検査 |
| 警察行政職員採用試験の内容 | |
| 第1次試験 | 【警察行政職員Ⅰ類】 教養試験、専門試験、論文試験 【専門職種Ⅰ類】 教養試験、専門試験、論文試験 【専門職種Ⅲ類】 教養試験、専門試験、作文試験 【警察行政職員Ⅲ類(事務)】 教養試験、作文試験 【警察行政職員Ⅲ類(電気)】 教養試験、専門試験、作文試験 【警察行政職員Ⅱ類】 教養試験、専門試験、論文試験 【技能系】 SPI3、作文試験、適性検査 【障害者を対象とする警察行政職員Ⅲ類】 教養試験、作文試験 |
| 第2次試験 | 【警察行政職員Ⅰ類(事務以外)】 【警察行政職員Ⅲ類(電気)】 【専門職種Ⅰ類/Ⅲ類】 【警察行政職員Ⅱ類】 面接試験(一般)、面接試験(専門)、身体検査、適性検査 【警察行政職員Ⅰ類(事務)】 【警察行政職員Ⅲ類(事務)】 面接試験(一般)、身体検査、適性検査 【技能系障害者を対象とする警察行政職員Ⅲ類】 面接試験、身体検査 |
それぞれの採用試験に合格した後は全員が「警察学校」に入り、警察官・警察職員として働くために必要な座学や訓練を受けます。
警察学校を卒業後、警察官・警察行政職員のキャリアがようやくスタート。警察官なら地域課に配属され、都内の警察署で勤めることになります。警察行政職員が配属される課は、各業務ごと異なります。
警察庁とは


警察庁は、日本の警察機関全体を統括・管理する「国」の行政機関(省庁)です。
全国の警察組織のトップであり、国家公務員が職員として勤めています。
警視庁と名前は似ていますが、警視庁が都民を守るのに対し、警察庁は日本という国全体の安全を守っています。
警察庁の仕事内容
警察庁の主な仕事内容は、各都道府県警察の運営・統括・指揮や、警察活動の基盤となる事務、警察行政の調整です。
犯罪捜査等で現場に立つことはなく、警察に関連する制度の企画・立案や、テロや国際犯罪の捜査支援、災害発生時の救助指導など、上流工程を担います。
警察庁で働くためには
警察庁で働くには、国家公務員試験を受験・合格した後、警察庁の官庁訪問を受け、そこで合格する必要があります。
受けられる国家公務員試験の種類を以下にまとめました。
| 試験区分 | 試験内容 |
|---|---|
| 総合職試験 (院卒者) | 【第1次試験】 基礎能力試験、専門試験(多肢選択) 【第2次試験】 専門試験(記述)、政策課題討議試験、人物試験 【英語試験】 |
| 総合職試験 (大学卒業程度) | 【第1次試験】 基礎能力試験、専門試験(多肢選択) 【第2次試験】 専門試験(記述)、政策課題討議試験、人物試験 【英語試験】 |
| 一般職試験 (大学卒業程度) | 【第1次試験】 基礎能力試験、専門試験(多肢選択)、 一般論文試験、専門試験(記述) 【第2次試験】 人物試験 |
| 一般職試験 (高校卒業程度・係員級) | 【第1次試験】 基礎能力試験、適性試験、 作文試験、専門試験(多肢選択) 【第2次試験】 人物試験、身体検査 |
国家公務員試験の合格ですら高難度ですが、そのうえ官庁訪問を受けて合格する必要があるため、警察庁で働くためには、非常に狭き門を通らなければなりません。
検察庁とは?
検察庁は全国に設置されており、最高位の「最高検察庁」をトップに「高等検察庁」「地方検察庁」「区検察庁」などが階層的に組織されています。
検察官は「公訴権」と呼ばれる唯一の起訴権限を持ち、刑事事件において被疑者を裁判にかけるかどうかを最終的に決定できる立場です。また、重大事件では警察に任せず、検察自らが直接捜査を行うこともあります。
検察庁の仕事内容
検察庁の主な仕事内容は、刑事事件の犯罪捜査や起訴不起訴の判断、公判活動などです。
まず、警察などが送致した事件について証拠を精査し、起訴か不起訴かを判断します。これを行うのが「検察官」で、刑事事件において唯一、起訴の判断を下せる立場です。
また、贈収賄事件や政治家が関与する重大事件などでは、検察自らが捜査を行う「直捜(ちょくそう)」を実施することもあります。起訴後は、公判で被告人の有罪を立証するために、法廷での主張・証拠提示などを行います。
検察庁で働くためには
検察庁で働くには、検察官にならなければいけません。検察官になるためには、司法試験合格後に司法修習を受ける必要があります。
ただ、司法試験は全員が受験できるわけではないため、以下の流れを理解しておくことが大切です。
- 予備試験に合格するor法科大学院で司法試験の受験資格を得る
- 司法試験に合格する
- 司法修習を受ける
- 検察庁で検察官として働く
司法試験の主な内容は、以下の表を参考にしてください。
| 試験区分 | 対象科目 | 配点/形式 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 短答式試験 | 民法、憲法、刑法 | 民法75点・憲法50点・刑法50点/四肢択一式 | 民法75分・憲法50分・刑法50分 |
| 論文式試験 | ■ 公法系:憲法・行政法 ■ 民事系:民法・商法・民事訴訟法 ■ 刑事系:刑法・刑事訴訟法 ■ 選択科目:倒産法・租税法・経済法・知的財産法・労働法・環境法・国際関係法(公/私)から1科目 | 各100点(選択科目は50点×2)/記述式 | 選択科目180分/他7科目各120分 |
また、司法試験合格後には1年間司法修習を受けなければいけません。司法修習では、検察官になるための採用活動を兼ねている場合も多いため、司法修習終了前から採用が始まっていることを理解しておきましょう。
公安とは


実は「公安」と名の付く組織には、内閣府に置かれる外局「国家公安委員会」や、法務省の「公安調査庁」、警備警察の部門の1つである「公安警察」(警視庁では公安部として独立している)の、3種類があります。
今回はその中でも、公安警察について詳しく解説していきます。
公安警察は他部門の警察官にすら本名と所属を名乗らず、予算の配分も非公開であるなど、秘密主義的な組織です。
公安の仕事内容
公安警察の主な仕事内容は、国家の安全を守るために、テロやスパイ活動を監視し、未然に防ぐことです。
国内的には右翼団体や宗教団体、学生運動、左翼の過激派への捜査・情報収集を行います。
その特殊な業務の性質上、捜査時には盗撮や盗聴など、違法行為もいとわないそうです。
スパイを監視する公安警察そのものが、スパイのような活動をしているんですね。
公安として働くには
公安警察になるためには、警察官採用試験や国家公務員試験に合格し、警察官としてのキャリアを積むことが必要です。
逆に、公安警察になるのに特殊な選考方法はなく、一般的な警察官と同様のステップで所属に至ります。
業務の性質が特殊であるため、なれるのは警察組織の中でもエリートのみといわれています。
都道府県警察とは?
都道府県警察は、各都道府県が管轄する警察組織です。警察庁の指導のもとで運営されていますが、基本的には各都道府県の公安委員会の管理下にあり、地方自治体に属する組織として位置付けられています。
都道府県警察は、地域社会の最前線で治安を守る中核的な存在であり、住民との距離が最も近い警察組織ともいえるでしょう。
都道府県警察の仕事内容
都道府県警察の主な仕事は、地域の安全と秩序を守ることです。具体的には、事件や事故への対応やパトロールによる犯罪の未然防止、交通違反の取り締まり、迷子や行方不明者の捜索、災害時の避難誘導など多岐にわたります。
身近に起きやすい犯罪だけでなく、組織犯罪や薬物事件、少年非行の対策、サイバー犯罪への対応など現代社会の変化に合わせた仕事にも対応します。警察官は、治安の維持だけでなく、住民の信頼を得ることも重要な使命とされており、地域との関係づくりも大切な仕事の1つです。
都道府県警察で働くためには
都道府県警察で働くためには、各都道府県が実施している「警察官採用試験」に合格する必要があります。警察官採用試験の内容は、警視庁の項目で紹介した内容と大きな違いはありません。
ただ、各都道府県によって試験問題や評価しているポイントが異なるため、受験前に確認しておくことが大切です。
また、警視庁と同じく、地方の警察本部でも警察学校へ入校します。警察学校の入校期間は、大体6〜10ヵ月となっており、採用区分によっても入校期間が異なるため注意が必要です。
各組織のトップは誰?
各組織の違いを理解する上で、各組織のトップは誰なのかを理解しておくことも大切です。各組織のトップに関しては、以下の通りです。
- 警視庁:警視総監
- 警察庁:警察庁長官
- 検察庁:検事総長
- 国家公安委員会:国務大臣
- 公安調査庁:公安調査庁長官
- 公安警察:警察庁警備局長または各都道府県警察本部の警備部長
- 都道府県警察:本部長(警視庁除く)
上記のように、それぞれの組織には明確な指揮官がおり、その立場や役割には大きな違いがあります。
「警察庁長官」や「検事総長」のように国全体を統括するポジションもあれば、「本部長」や「警視総監」のように地域を単位とした現場組織のトップも存在します。
また、警察系組織と検察庁・国家公安委員会では所属する省庁や組織体系が異なるため、同じ「トップ」という表現でも、その管轄や業務の性質には注意が必要です。



気になる方はそれぞれがどう違うのかも調べてみるのがおすすめです!
各組織のおける関係性と組織図
ここまで紹介した5つの組織は、全てが独立して活動しているわけではありません。法制度や役割に応じて連携・監督関係が明確に構築されています。
各組織に関する関係性について知りたい方は、以下を参考にしてください。
「警察庁」は全国の都道府県警察を指導・監督する国家機関であり、「都道府県警察」は地域に根差した現場対応を担います。「警視庁」も都道府県警察の一部です。
また、警察が行う捜査活動の一部は「検察庁」に送致され、検察官が起訴・不起訴を判断します。このように、警察と検察は犯罪捜査における協力関係にあります。
一方で、「公安調査庁」はスパイやテロ、過激派などに対する情報調査を担い、警察や検察とは分野は異なりますが、国家の治安維持という点で密接な情報連携が行われているのが特徴です。



それぞれがどんな役割を持ち連携しているのかを組織図で理解しておきましょう!
まとめ
警視庁・警察庁・公安はそれぞれ同じ警察行政機関ではありますが、管轄や業務内容は大きく異なります。
警察庁は日本の警察全体を統括し、警視庁は都の治安維持はもちろん、国際的な要人の警護等も担い、公安警察はテロやスパイを監視し未然に防ぐのが主な業務です。
それぞれなり方や目指す方向が違うため、もし現在「警察に関わる仕事をしたいけれど、どの機関で働くのかまでは定まっていない」という人は、違いを理解して今後のキャリアパス形成の参考にしてみてはいかがでしょうか。
\警視庁採用試験の情報を発信/
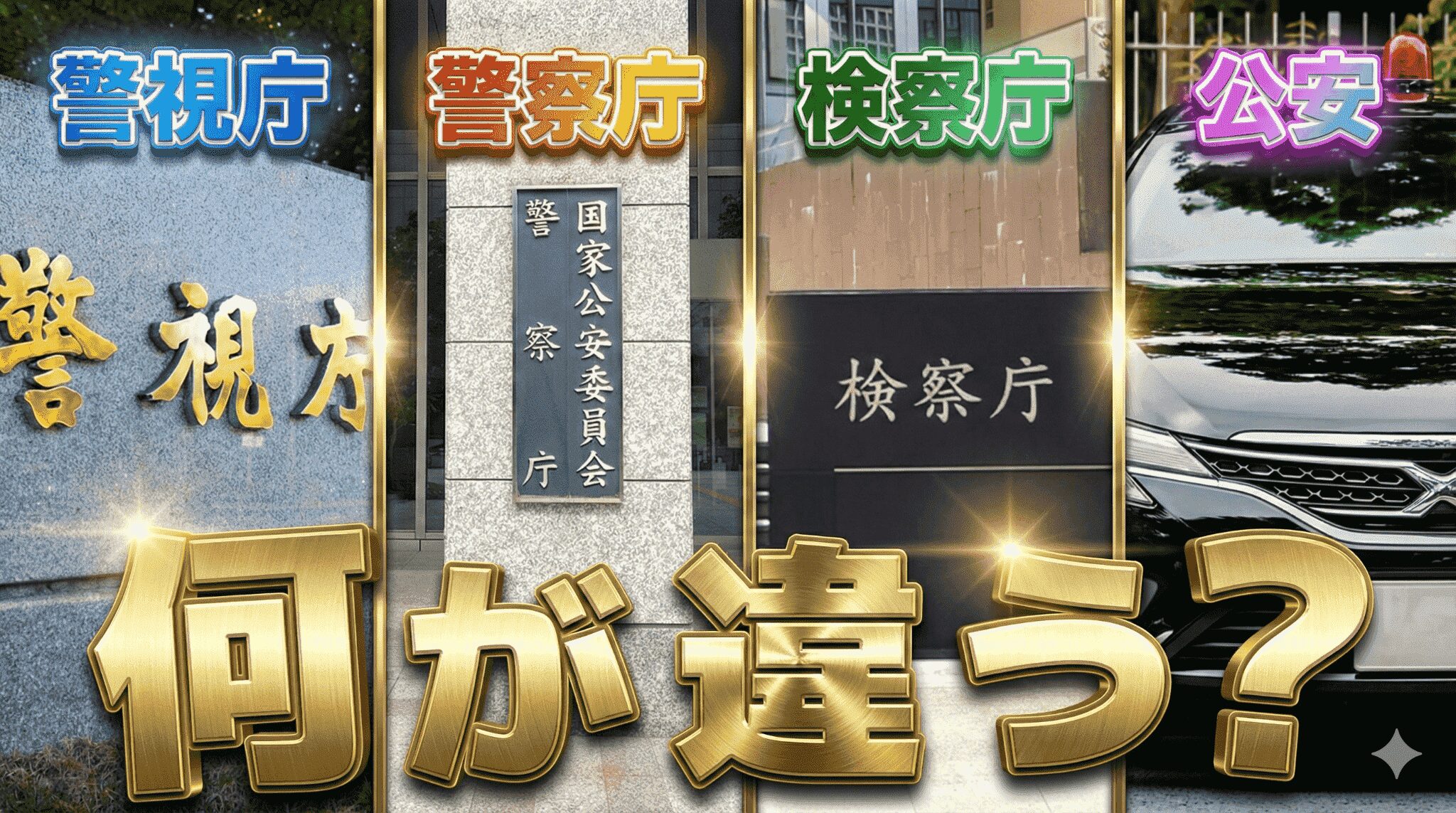



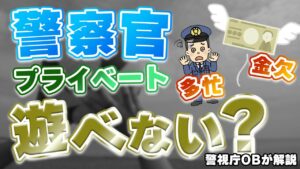
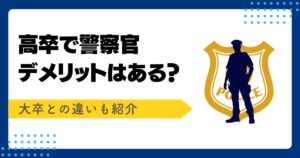



コメント
コメント一覧 (2件)
こんにちは。
小学6年生女子です。
私は警察官に憧れていて、自由研究のお題を、「警察官について」にしました。このサイトはいつも使わせてもらっています。ありがとうございます。いつか私も、警察官になる時のために、今のうちから勉強をしています。
ありがとうございます!将来素敵な警察官になってください(*^^*)