 安齋
安齋警察官採用試験の合格に特化したオンラインスクール「警志塾」を運営している安齋です!
警視庁の2次試験では、体力試験が実施されます。
体力に自信が無い人ほど「体力試験で不合格になるのではないか…」と不安に感じてしまうかもしれません。
しかし、警視庁の体力試験難易度は低く、正しい理解と対策ができていれば、合格する可能性は十分にあります。
今回は、警視庁の体力試験内容や対策法、合格基準などを細かく解説します。
記事の後半には警視庁に最終合格する最重要ポイントを解説しているので、体力試験を控えている方は最後までご覧ください。
\ 無料で特典を受け取ろう /
警視庁の体力試験概要
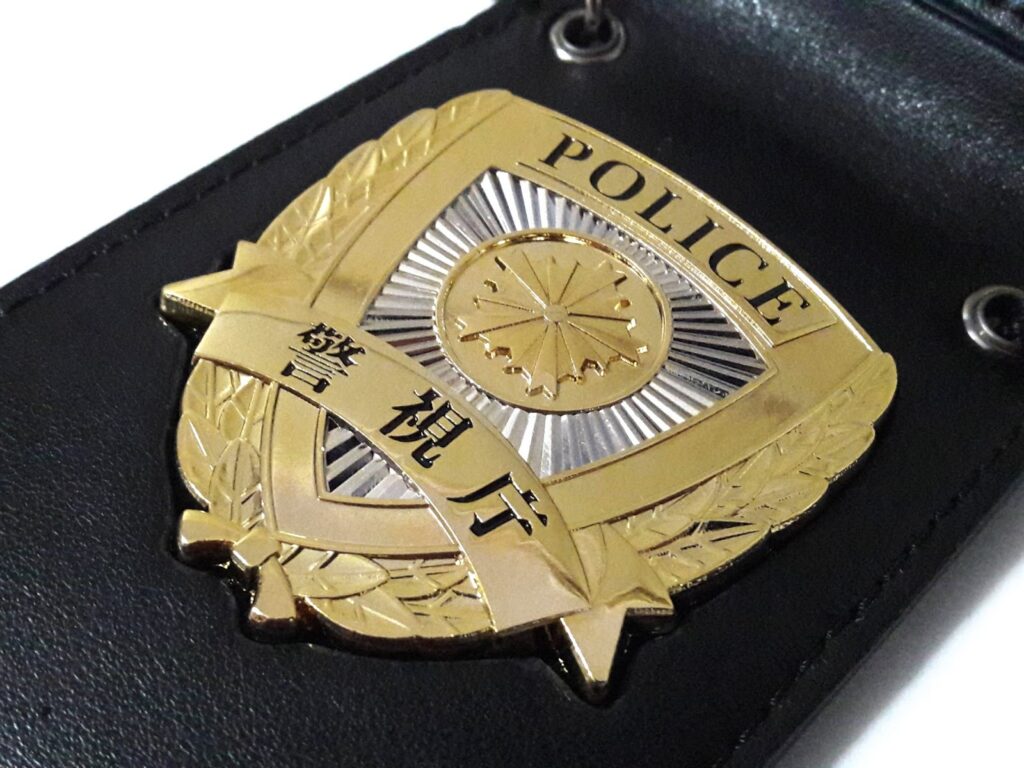
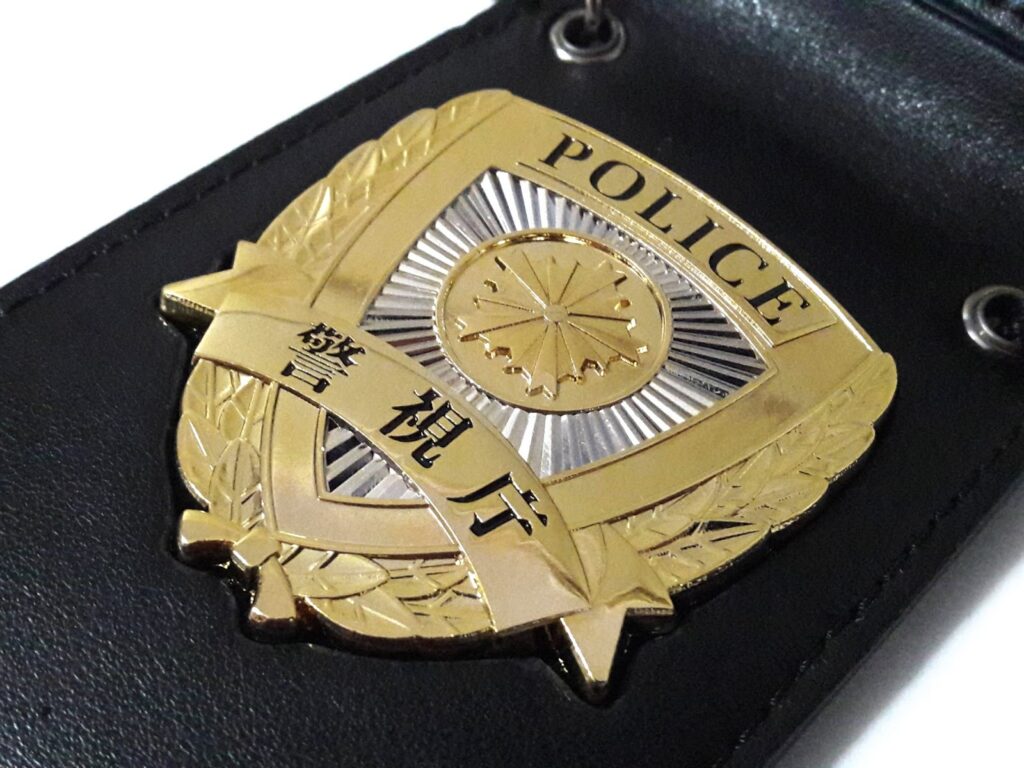
警視庁の体力試験は、毎年2次試験で実施されており、身体検査や面接試験も同日に実施されます。
令和7年度に実施された警視庁2次試験内容は、以下表を参考にしてください。
| 試験科目 | 概要 | 詳細 |
|---|---|---|
| 面接試験 | 人物についての面接試験 | |
| 身体検査 | 検査内容 | 視力検査、色覚検査、聴力検査、運動機能の検査、医師の診察、身長測定、体重測定、レントゲン検査、血液検査(貧血検査、肝機能検査、血中脂質等検査、血糖検査)、尿検査 |
| 視力 | 裸眼視力が両眼とも0.6以上、又は矯正視力が両眼とも1.0以上であること | |
| 色覚/聴力 | 警察官としての職務執行に支障がないこと | |
| 疾患 | 警察官としての職務執行上、支障のある疾患がないこと | |
| その他身体の運動機能 | 警察官としての職務執行に支障がないこと | |
| 体力試験 | 腕立て伏せ、バーピーテスト、上体起こし、反復横跳び | |
身体検査は、警察官として職務を執行する際に疾患等が無いかを確認するためのものです。
そして、面接試験では個別面接が行われます。
2次試験に合格するためには面接試験対策も重要になるため、体力試験と並行して対策しておいてください。



面接試験について知りたい方は、以下記事を確認してください!
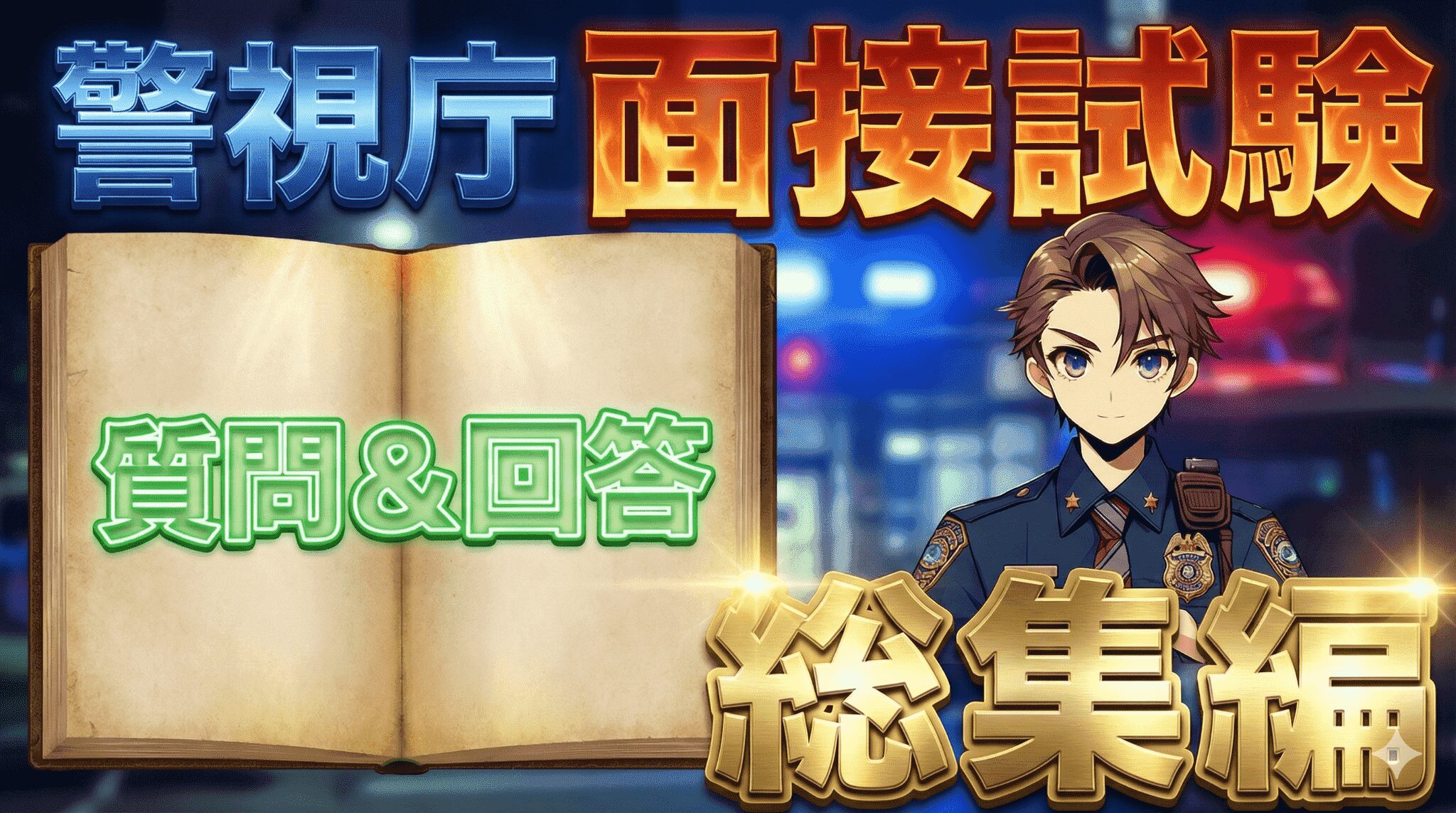
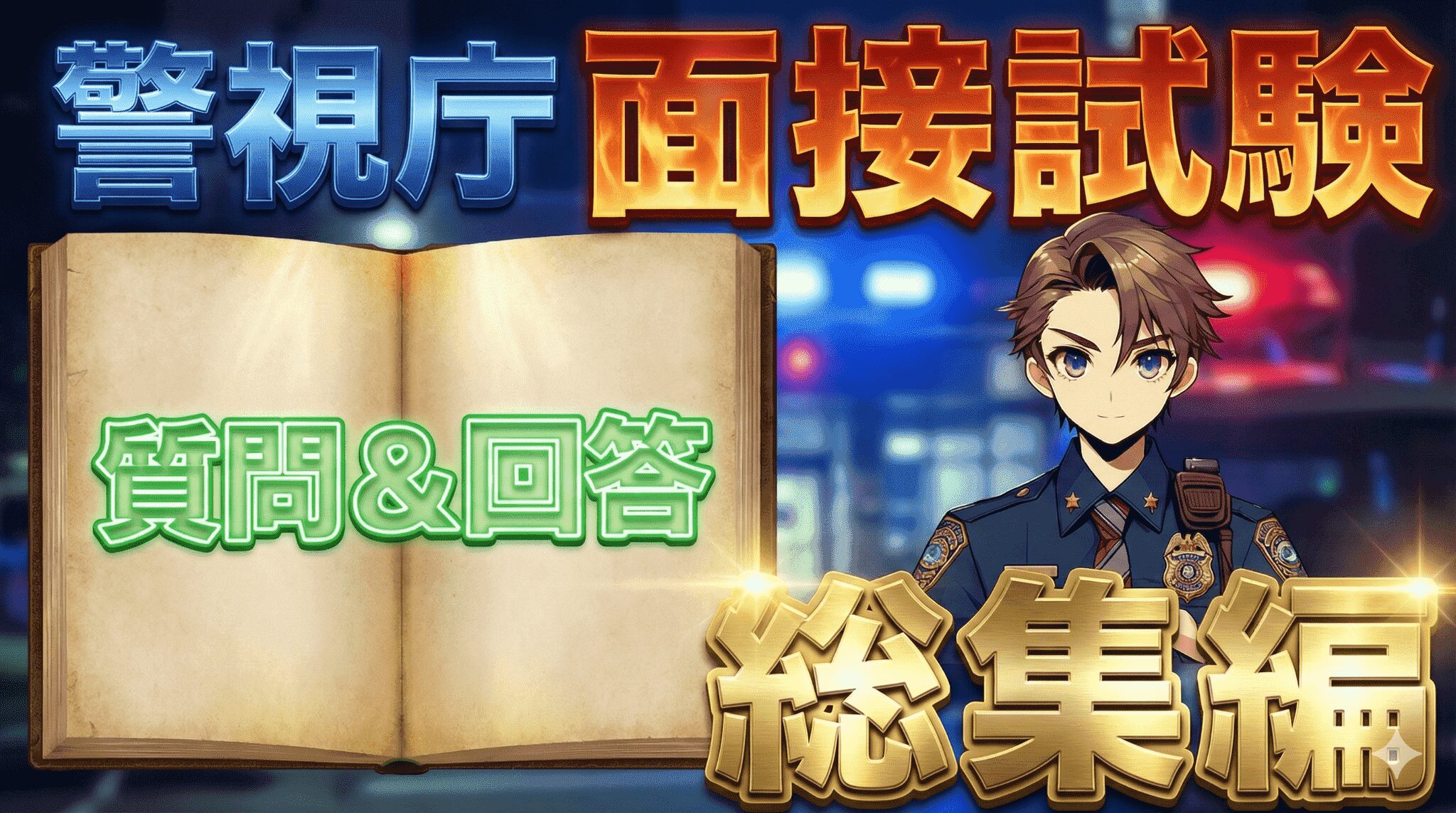
配点
警視庁体力試験の配点は、公式サイトで発表されていません。(令和7年度時点)
しかし、体力試験の配点は採用試験全体でそれほど高くないと考えられており、他の都道府県の配点を見ても明らかです。
都道府県別の体力試験の配点と割合は、以下表を参考にしてください。
| 都道府県 | 体力検査 | 総合得点 | 体力検査割合 |
|---|---|---|---|
| 青森県警 | 40点 | 335点 | 11.9% |
| 岩手県警 | 40点 | 660点 | 6.1% |
| 秋田県警 | 100点 | 600点 | 16.7% |
| 山形県警 | 100点 | 800(820)点 | 約12.5% |
| 茨城県警 | 60点 | 600点 | 10.0% |
| 群馬県警 | 200点 | 1230点 | 16.3% |
| 埼玉県警 | 200点 | 705点 | 28.4% |
| 長野県警 | 150点 | 1700点 | 8.8% |
| 富山県警 | 20点 | 410点 | 4.9% |
| 石川県警 | 80点 | 1600点 | 5.0% |
| 静岡県警 | 150点 | 906~924点 | 約16.6% |
| 三重県警 | 40点 | 365点 | 11.0% |
| 京都府警 | 50点 | 650点 | 7.7% |
| 奈良県警 | 100点 | 1580点 | 6.3% |
| 島根県警 | 90点 | 1000点 | 9.0% |
| 岡山県警 | 40点 | 585~590点 | 約6.8% |
| 広島県警 | 40点 | 235点 | 17.0% |
| 徳島県警 | 50点 | 300点 | 16.7% |
| 香川県警 | 100点 | 880点 | 11.4% |
| 愛媛県警 | 16点 | 176点 | 9.1% |
| 高知県警 | 20点 | 300点 | 6.7% |
| 佐賀県警 | 40点 | 610点 | 6.6% |
| 熊本県警 | 30点 | 600点 | 5.0% |
| 大分県警 | 100点 | 580点 | 17.2% |
| 宮崎県警 | 40点 | 415点 | 9.6% |
| 沖縄県警 | 20点 | 246点 | 8.1% |
参考:令和6年度受験案内 – 警察官A(男性)・警察官A(女性)採用試験
参考:採用試験受験案内 警 察 官 B 女性警察官B
参考:令和7年度 受験案内 警察官B採用試験
参考:試験概要/茨城県警察|採用案内
参考:令和7年度第2回群馬県警察官採用試験
参考:令和7年度 埼玉県警察官(巡査)採用試験案内
参考:令和7年度長野県警察官採用試験案内
参考:第1回警察官採用試験
参考:令 和 7 年 度 警 察 官 B 採 用 候 補 者 試 験 案 内 (高校卒程度)
参考:静岡県警察官採用試験(第1回)案内
参考:警察官B採用候補者試験 受験案内
参考:令和7年度 第1回京都府警察官採用試験案内
参考:奈良県警察官(第1回)採用試験案内
参考:令和7年度 島根県警察官A(高校卒業程度)採用試験 受 験 案 内
参考:警察官採用情報 – 岡山県警察 採用情報
参考:令和7年度広島県警察官採用試験案内
参考:令和7年度徳島県警察官採用試験案内
参考:大阪府・兵庫県警察官B採用試験
参考:令和7年度愛媛県警察官(高校卒程度)採用候補者試験案内
参考:令和7年度高知県警察官採用試験案内
参考:令和7年度佐賀県警察官採用試験案内
参考:警察官採用試験案内
参考:令和7年度大分県警察官採用試験案内
参考:令和7年度宮崎県警察官採用試験案内
参考:令和7年度 – 沖縄県警察官B(高卒程度)採用試験案内



以上の表は、公式サイトに体力試験の点数が記載されていた都道府県のみを掲載しています!
都道府県によって若干の違いはありますが、ほとんどの都道府県で体力試験の配点が5〜20%程度となっています。
つまり、最低限合格基準に達している場合、体力試験で不合格になる可能性は低いと言えるでしょう。
ただ、全く対策をしていないと不合格になる可能性はあるため、適切な方法で対策することが大切です。
倍率
体力試験に合格するためには、倍率についてもある程度理解しておくことが大切です。
ただ、警視庁の公式サイトには体力試験の倍率に関する記載はありません。
参考として、神奈川県警の2次試験倍率を以下にまとめたので、気になる方は確認してください。
| 実施年度 | 試験区分 | 2次試験受験者数 | 最終合格者数 | 2次試験倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 警察官B(男性) | 570名 | 282名 | 2.0倍 |
| 警察官B(女性) | 179名 | 110名 | 1.6倍 | |
| 令和6年度 | 警察官B(男性) | 883名 | 345名 | 2.5倍 |
| 警察官B(女性) | 284名 | 126名 | 2.6倍 |
以上の表は、各年度での第1回及び第2回を合計した数になります。(令和7年10月時点)
倍率は1.6〜2.6倍となっているため、2人に1人程度は不合格になる可能性が高いです。
ただ、2次試験では面接試験も実施されているため、一概に体力試験だけの結果というわけではありません。
そのため、倍率は参考程度にし、面接試験対策も怠らないことが大切です。



執筆時点で令和7年度第2回試験結果が出ていないため、今後数値の変動があります!
合格基準
体力試験対策をする際には、合格基準がどの程度かも理解しておくことが大切です。
ただ、配点同様に警視庁では体力試験の明確な合格基準は公開されていません。
そのため、他の都道府県警察の合格基準を参考にし、体力試験対策を進める必要があります。
以下は、香川県警察の体力試験基準表です。
| 種目 | 性別 | 0点 | 5点 | 10点 | 15点 | 20点 | 25点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 握力 | 男性 | 35㎏以下 | 36~40㎏ | 41~45㎏ | 46~50㎏ | 51~55㎏ | 56㎏以上 |
| 女性 | 19㎏以下 | 20~22㎏ | 23~26㎏ | 27~30㎏ | 31~34㎏ | 35㎏以上 | |
| 腕立て伏せ | 男性 | 14回以下 | 15~20回 | 21~27回 | 28~34回 | 35~41回 | 42回以上 |
| 女性 | 8回以下 | 9~14回 | 15~21回 | 22~28回 | 29~35回 | 36回以上 | |
| 反復横跳び | 男性 | 41回以下 | 42~45回 | 46~49回 | 50~54回 | 55~59回 | 60回以上 |
| 女性 | 35回以下 | 36~39回 | 40~43回 | 44~47回 | 48~51回 | 52回以上 | |
| 立ち幅跳び | 男性 | 195㎝以下 | 196~211㎝ | 212~227㎝ | 228~243㎝ | 244~259㎝ | 260㎝以上 |
| 女性 | 159㎝以下 | 160~169㎝ | 170~179㎝ | 180~190㎝ | 191~201㎝ | 202㎝以上 |
香川県警察の場合、100点満点中男女とも25点に達しない場合は不合格になります。
つまり、総合得点の25点以下は足切りということです。
警視庁では握力や立ち幅跳びは実施されませんが、他の項目は香川県警察と似た基準で評価されている可能性が高いです。
可能な方は、過去の警視庁合格者の意見を参考にし、どの程度の基準を満たしていれば良いかを確認しておいてください。



新体力テストの基準なども確認しておくと、対策時の目安にしやすいです!
警視庁の体力試験内容と対策法


警視庁の体力試験で実施される種目は、以下の4つです。
- 腕立て伏せ
- バーピーテスト
- 上体起こし
- 反復横跳び
各種目の内容だけでなく、対策法を理解しておくことで効率的に対策を進められます。
警視庁以外の採用試験でも役立つ方法のため、他の都道府県を受験する方も確認しておいてください。



腕立て伏せや上体起こしは、多くの都道府県警察の体力試験で採用されている種目です!
腕立て伏せ
腕立て伏せは、警視庁の体力試験で上半身の筋力と持久力を測定する種目です。
男女ともに行われ、一定のテンポに合わせてどれだけ多く回数をこなせるかが評価されています。
「指示通りの姿勢でできていない」又は「号令に遅れる」などはカウントされないため、注意してください。
| 【対策のポイント】 |
|---|
| 腕立て伏せを練習する際には、腕を伸ばした状態から胸が地面に付く程度まで下げることが大切です。 疲れてきても姿勢を崩さず、1回でも多くできるように対策しておいてください。 また、2秒に1回のペースで60秒間(30回)程度できるように練習するのがおすすめです。 練習の段階では、インターバルを挟んで複数セット行うことで、徐々に身体を慣らすことができます。 |
腕立て伏せの詳細に関しては、佐賀県警察のYouTubeでも紹介されているため、気になる方は確認してみてください。



大まかなイメージを動画で掴みましょう!
バーピーテスト
バーピーテストは、全身の持久力や瞬発力、リズム感などを評価する種目です。
指定された時間内に、何回実施できるかで評価しています。
一般的なバーピーでは跳躍を挟みますが、警視庁を含む多くの警察官採用試験では立ち上がるまでで1回とカウントされるのが特徴です。
| 【対策のポイント】 |
|---|
| バーピーテストでは、無理にスピードを上げると姿勢が崩れやすく減点に繋がるため、スピードよりも正確性を意識することが大切です。 また、バーピーだけを練習するよりも、心肺機能を高めるためのランニングやHIIT(高強度インターバルトレーニング)を取り入れることで基礎体力向上に繋がります。 |
バーピーテストに関しては、神奈川県警察の公式YouTubeチャンネルが以下動画を公開しているので、参考にしてみてください。



腕立て伏せと同様に姿勢が重要視されるため、練習の段階から意識してください!
上体起こし
上体起こしは、腹筋の筋持久力を測定する種目です。
30秒間での回数を測定し、背中が床にしっかり付いた状態から、肘を両膝に付けるまでを1回としてカウントします。
反動を使ったり、腕の勢いで起き上がったりするとカウントされないため注意してください。
| 【対策のポイント】 |
|---|
| 腹筋では、正面の腹直筋だけでなく、腹斜筋や腹横筋なども一緒に鍛えるのが効果的です。 上体を真っすぐ上げるだけでなく、捻りながら上げるなど工夫することで筋持久力を高めやすくなります。 また、補助要員がいない状態(足の支えが無い状態)で行われることもあるため、1人でできるように対策しておくのがポイントです。 |



上体起こしのやり方も神奈川県警察の公式YouTubeで紹介されているので、参考にしてみてください!
反復横跳び
反復横跳びは、俊敏性やバランス力、下半身の瞬発力を評価する種目です。
床に引かれた3本のラインのうち、中央線を跨ぐように左右へ素早く移動し、20秒間での回数を測定します。
回数を稼ごうとするあまり、「左右の線に足が触れずにカウントされなかった」というケースも多いため、急ぎつつも正確に行うことが大切です。
| 【対策のポイント】 |
|---|
| 反復横跳びでは、ステップの幅とテンポを一定に保つことを意識してください。 焦って大きく動くよりも、無駄のない動きで素早く切り返すことが回数アップに繋がりやすいです。 また、マーカーやテープでラインを引けば自宅でも練習できるため、スピードやテンポなどに慣れておくことをおすすめします。 |



福島県警察の公式YouTubeで、反復横跳びのやり方について紹介されています!
警視庁の体力検査に必要な持ち物


警視庁の2次試験では、体力試験だけでなく面接試験も実施されます。
そのため、スーツで試験会場に行き、身体検査や体力試験の際に運動着に着替えるのが通例です。
警視庁の体力試験での持ち物は、以下を参考にしてください。
- トレーニングウェア、ジャージ
- 靴下
- 室内用シューズ(必要に応じて)
- タオル
また、警視庁の体力試験は武道場で行うケースが多いため、運動靴は必要無いのも特徴です。
体育館を利用する場合には、2次試験の持ち物に運動靴が指定されるため、室内用シューズを持参してください。



体力試験か面接試験のどちらが先かは人によって異なるため、靴下やインナーなど予備を持っておくことをおすすめします!
体力試験でおすすめの対策法


体力試験でおすすめの対策法としては、以下の3つが挙げられます。
- 苦手種目を中心に対策する
- 実際の計測方法で練習する
- 過去に合格経験のある方にアドバイスしてもらう
何も考えず対策するよりも、効率的な方法で対策することでより高い効果を実感できます。
これらの方法を参考にすることで、「体力試験対策に多くの時間を割けない」と感じている方も、最低限の対策ができるでしょう。



私が試して実際に効果があると感じたものを紹介します!
苦手種目を中心に対策する
警視庁の体力試験でおすすめの対策法として、苦手種目を中心に対策するということが挙げられます。
体力試験では、複数の種目をもとに総合的に評価されています。
そのため、得意種目だけを伸ばすよりも、苦手種目を重点的に強化することが合格への近道です。
また、苦手種目を放置したことが明らかだと、人物評価に影響する可能性も捨てきれません。
まずは、過去の受験者の平均記録と自分の記録を比較した上で、どの種目が苦手なのかを可視化することから始めてみてください。



2次試験では、体力試験に加え面接試験など、総合的な結果を見て判断されることを理解しておきましょう!
実際の計測方法で練習する
警視庁の体力試験でおすすめの対策法として、実際の計測方法で練習するということが挙げられます。
警視庁に限らず警察官採用試験の体力試験では、各種目の計測方法や姿勢、制限時間などが細かく定められていることが多いです。
例えば、上体起こしでは反動を使わない、腕立て伏せは一定のペースで行うなどが挙げられます。
自己流で対策していても、本番のやり方に慣れていないと、思うような結果が残せない可能性も高いです。
そのため、日頃から実際の計測方法で練習し、本番でも100%の力を発揮できるように対策しておいてください。



同じ種目でも計測方法は都道府県によって異なるため、過去の情報をもとに実際の計測方法を調査しておいてください!
過去に合格経験のある方にアドバイスしてもらう
警視庁の体力試験でおすすめの対策法として、過去に合格経験のある方にアドバイスしてもらうということが挙げられます。
体力試験では、数字上の基準だけでは分からない実践的なコツや注意点も多くあります。
特に、当日の雰囲気や他の受験者の様子などは、実際に試験に参加した方しかわからないため、合格経験のある方のアドバイスは非常に有効です。
ただ、身近に合格経験のある方もしくは現役の警察官がいるというケースも少ないでしょう。
そのような場合は、警察官採用試験の予備校を活用するのがおすすめです。
中でも警志塾は、警視庁OBが講師として在籍しているため、採用試験だけでなく合格後のリアルな様子についてもアドバイスを受けられます。
体力試験だけでなく、筆記試験や面接試験対策にも対応しているため、まずは無料相談で自分の目的に合うかどうかを確認してみてください。



警志塾の公式LINEを追加することで無料相談が行えます!
\ 無料で特典を受け取ろう /
警視庁の体力試験に関するよくある質問


警視庁の体力試験に関するよくある質問をまとめたので、気になる方は参考にしてください。
- 体力試験に足切りはある?
-
警視庁の体力試験では、明確な「足切り基準」は公表されていません。
ただ、極端に低い記録や測定時に棄権・失格となった場合は不合格の大きな要員となる恐れがあります。
そのため、最低限の合格基準を理解した上で対策しておくことが大切です。
- 男女で試験内容に違いはある?
-
警視庁の体力試験では、男女で試験内容に違いはありません。
ただ、合格基準は女性の方がやや低く設定されていると考えられています。
※公式発表が無いため正確には不明です。
- 体力試験が原因で不合格になることはある?
-
体力試験のみで不合格になるケースは少ないですが、平均点以下だと総合評価の中で不利になる可能性が高いです。
体力試験が原因で不合格になることが無いように、苦手種目を対策した上で、総合得点を高めておきましょう。
- 体力試験の合否はいつ発表される?
-
警視庁の体力試験の結果は、2次試験の合格発表としてまとめて発表されます。
体力試験だけの合否は個別に発表されないため、受験者が確認できるのは全体の結果通知だけです。
- 体力試験にはどんな靴(服装)で行けば良い?
-
試験会場自体には、スーツで臨むのが一般的です。
身体検査や体力試験の際には着替える必要があり、動きやすいトレーニングウェアと運動靴をおすすめします。
ただ、受験先によって服装指定や運動靴が不要な場合があるため、事前に確認しておいてください。
警視庁に合格したいなら体力試験以外にも対策が必要
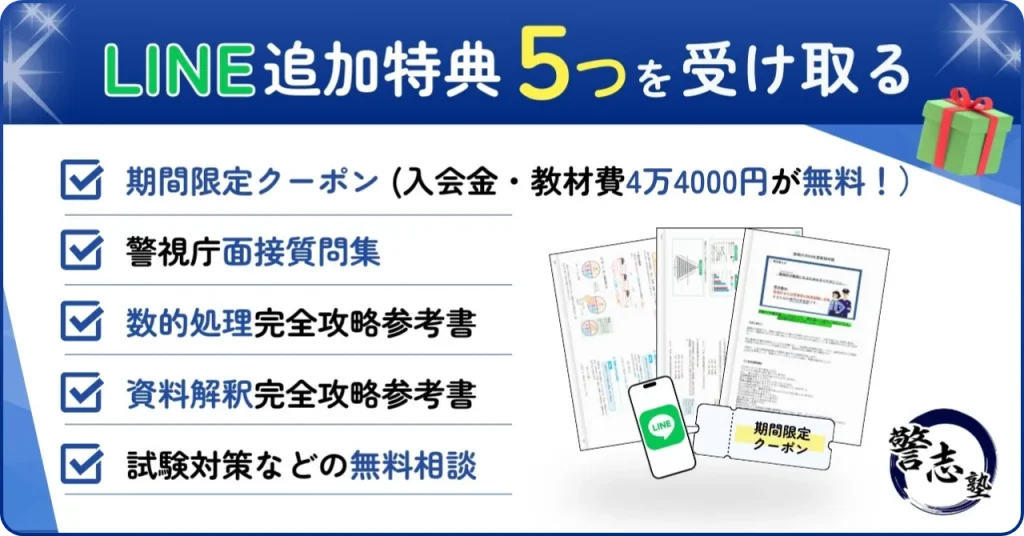
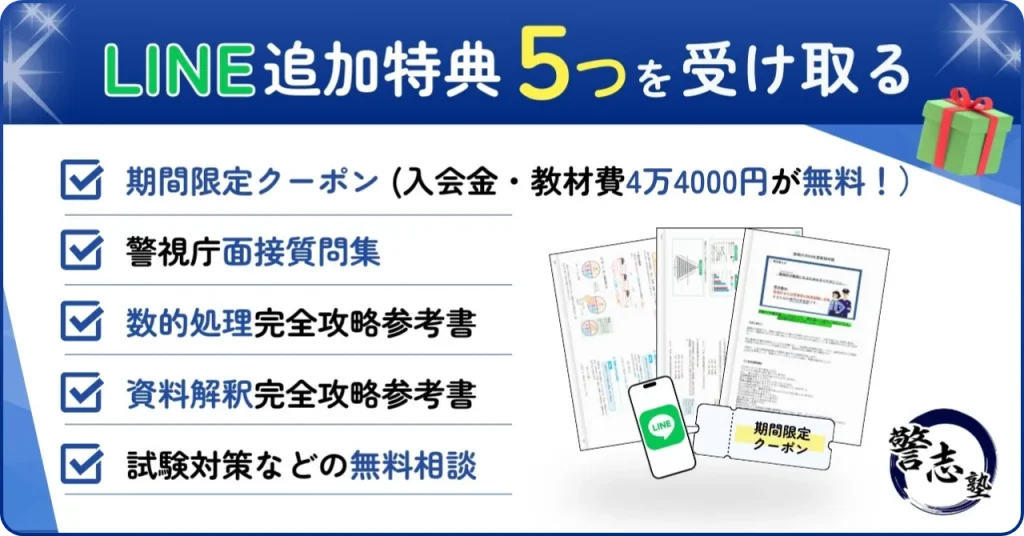
警視庁の体力試験は、適切な対策ができていれば十分合格基準を満たせます。
毎日コツコツと対策しておけば問題無い程度の試験でもあるため、今回の内容を参考に必ず対策しておいてください。
ただ、警視庁に合格したいなら体力試験以外にも対策が必要です。
特に2次試験では、面接試験の方が重要視される傾向にあるため、体力試験と並行して面接試験対策にも力を入れてください。
警志塾の面接対策では、オンラインで警察官採用試験合格者指導のもと模擬面接を行えます。
細かい部分のフィードバックもしてもらえるため、自宅から手軽に面接力を向上させられるでしょう。



公式LINEでは無料相談も受け付けており、体力試験の相談も可能です!
\ 無料で特典を受け取ろう /
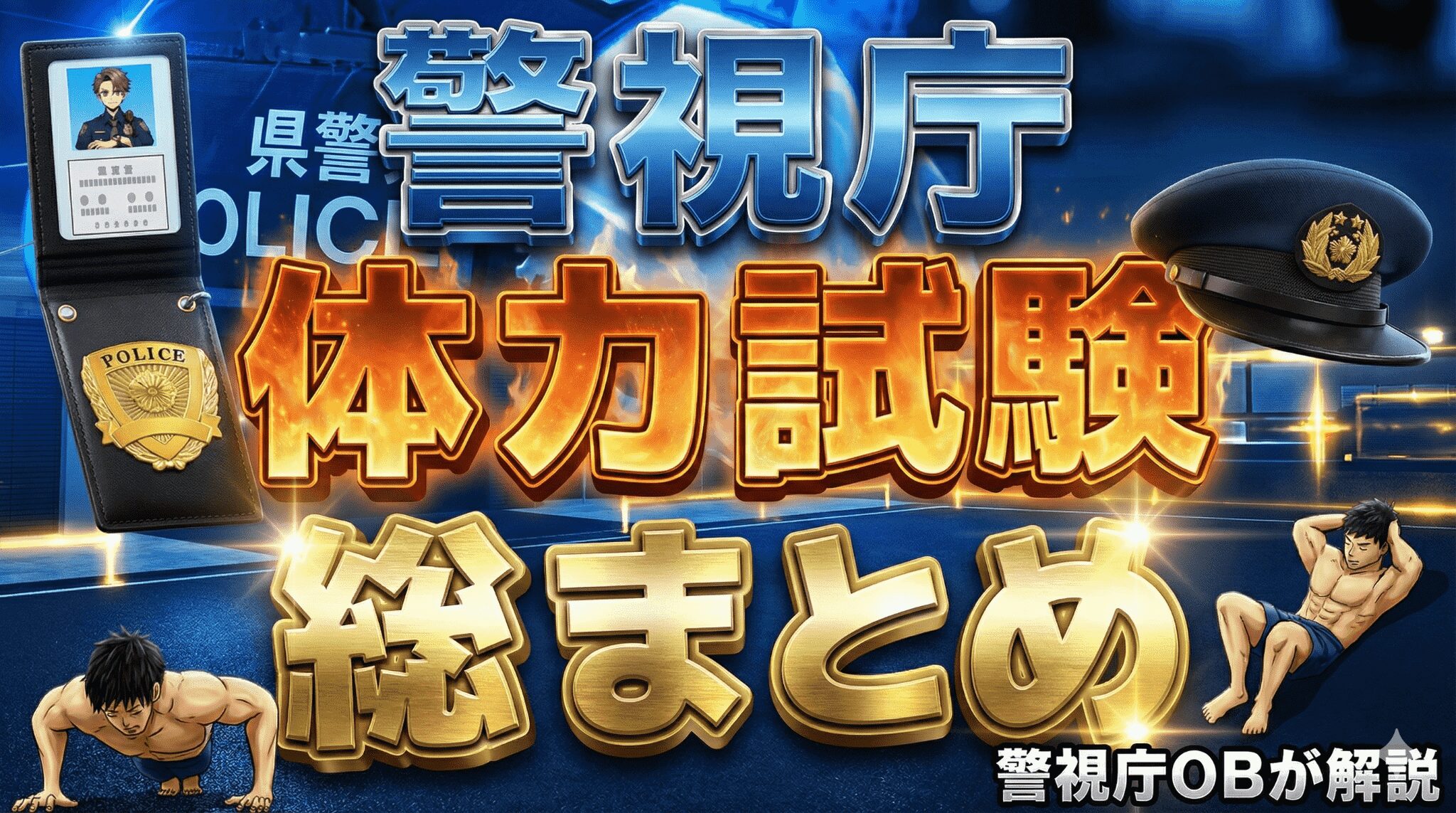
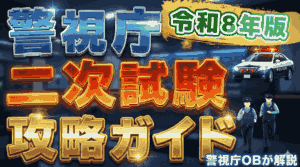
コメント